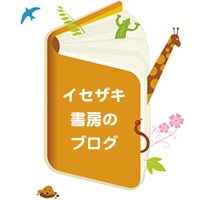これは確かにつらい現実の問題だと思う。
私は長年いつも注意して見ている事がある。それは商店の店頭に『アルバイト募集 時給○○円』という求人広告の下げ札のかかり方の様子である。これが多くなってくると「今、求人は難しいな」と考え、それがあまり見当たらなくなってくると「今なら求人出来るな」と思ってきた。
零細小売店はみなそうかも分からないけど(書店)などという荒利の少い小売業は人件費にも限界があり、いつもそれを注意していないとやってゆけないのが現実である。
テレビや新聞でこんなに人が余っているのに手間がなくて困っている所が今現在も沢山ある。勿論、職種を選ぶのは当然だと思うし、より安定した職場を望むのも私にもよく分る。
でもなぜか、人余り時代というのに人手不足の所が多いというのは何がそうさせているのだろうか。
私は求職者の事を詳しく調べた訳でもないのでよく分らないというのが本当のところである。
私は生まれた時から戦争していたし戦争の中で育ち物心つきかねた時、敗戦により占領下の中で小・中・高を過ごし高校三年の秋、やっと独立国になった。そんな時代に国民が生きてゆくには働かなくてはならなかった。
又、衣も食も住も自分の手を使わざるを得なかった。
例えば学校の制服も古着を染めて手造り。食事は貧しいながらも色々考え、米の粉を石臼で引いて作りおだんごを造るとか。雨漏りがすれば屋根瓦を置きなおして自分で修理する。停電すれば開閉器を開けて自分でヒューズを直す。季節が変る毎に母は子供の為の着る物を縫ったり編んだりして準備する。子供もそれを手伝いながら方法を覚えてゆく。
こんな少女時代をすごした人間にとっては当り前と思う事が時々出来ない若者に出会ってとまどう事があった。例えば店の蛍光灯が切れた時「取りかえてほしい」と云うと「やり方が分らない。やった事がない」という大学生に何度も出会って驚いた。そして更に先輩達は「普通ですよ、みんな出来ないですよ」とすました顔をしているのに又、驚いた。
これはほんの一例。手を使って何々をするという事がほとんど未経験の人間が増えてきた。
ものづくり日本と胸をはって云えるのは丁度今、定年退職してゆく年代までのような気がしてきた。
器用な人間が減ってしまった。
もちろん例外もあるが総じて気力に乏しく外見を飾り立てる事しか力を注がない人間がふえてきた。じっくり本を読むという若者が減ってしまった。
東南アジアの中で群を抜いて優秀な技量、経験、やる気を持っていた日本人はそろそろ第一線から消えてしまいそうな不安も感じる。教育が原因だったのか少しばかり成金(高度成長期)になったおかげで貧困時代を忘れたのか分らないけどもっと日本人は誠実に働くという事を思い起こそうではありませんか。
働くという事を忘れないでほしいです。
私は何度も書くが休日が多すぎます。
高速道路のどこまでも¥1000というのも休日だけというのは間違っていると思う。普通の日こそ値下げして物流の車を楽にしてしかるべきだと思います。
政府が率先して遊ぶ時間を提供しなくても日本人は遊ぶ人は充分遊んでます。
本当に困ってる人の事を少しばかり選挙のためにあちこち周っても真実はつかみ切れておりません。日本人はもっと働く事に意義を見出そう
内面の充実に力を注ごう。それには先ず本を読む事です。
私の好きな本を並べてみます。
興味のある方はぜひ、読んでみて下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「午後の曳航」
改版
新潮文庫
三島由紀夫/著
出版社名 新潮社
税込価格 380円

「駅路」
改版
新潮文庫 傑作短編集 6
松本清張/著
税込価格 660円

「容疑者Xの献身」
東野圭吾/著
出版社名 文芸春秋
税込価格 660円

「ダブル・ファンタジー」
村山由佳/著
出版社名 文芸春秋
出版年月 2009年1月
税込価格 1,780円
-----------------------------------
イセザキ書房
〒231-0055 神奈川県横浜市中区末吉町1-23
TEL: 045-261-3308 FAX: 045-261-3309
www.isezaki-book.com
お問い合わせ・ご注文フォーム
 「美食の道」
「美食の道」









 ※地図参照
※地図参照
 「共生経済が始まる」
「共生経済が始まる」